楽器メーカーが浜松市に集中しているのはナゼ?
ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

 フランツ・リスト
わざわざ難しいとされているリストですよ。
さらに、
途中でジェリーが弾いているジャズナンバーは、
『On the Atchison Topeka and the Santa Fe』
(サンタフェ鉄道)といって
1946年の米ミュージカル映画『The Harvey Girls』の挿入歌で、
アカデミー主題歌賞を受賞した大ヒットした曲なんだそうです。
なんか当時の雰囲気が味わえて、いい曲ですネ。
トムとジェリーのBGMにも近い感じがします。
というわけで、
「トムとジェリー」の『ピアノコンサート』は、
音楽的にも完成度が高くて、
今見ても全然楽しめる作品ですよね。
世界的なピアニストである中国の郎朗(ランラン)さんは、
小さい頃にこの「トムとジェリー」の『ピアノコンサート』に衝撃を受けて、
ピアニストを志したんだとか。
なんとも影響力のある作品です。
ちなみに、「トムとジェリー」の1940年〜1953年までの作品は
日本での著作権保護期間が終了しているんだそうです。
「ピアノコンサート」の公開日は1947年4月26日です。
参考:
フランツ・リスト
わざわざ難しいとされているリストですよ。
さらに、
途中でジェリーが弾いているジャズナンバーは、
『On the Atchison Topeka and the Santa Fe』
(サンタフェ鉄道)といって
1946年の米ミュージカル映画『The Harvey Girls』の挿入歌で、
アカデミー主題歌賞を受賞した大ヒットした曲なんだそうです。
なんか当時の雰囲気が味わえて、いい曲ですネ。
トムとジェリーのBGMにも近い感じがします。
というわけで、
「トムとジェリー」の『ピアノコンサート』は、
音楽的にも完成度が高くて、
今見ても全然楽しめる作品ですよね。
世界的なピアニストである中国の郎朗(ランラン)さんは、
小さい頃にこの「トムとジェリー」の『ピアノコンサート』に衝撃を受けて、
ピアニストを志したんだとか。
なんとも影響力のある作品です。
ちなみに、「トムとジェリー」の1940年〜1953年までの作品は
日本での著作権保護期間が終了しているんだそうです。
「ピアノコンサート」の公開日は1947年4月26日です。
参考:
この記事にはまだコメントがありません。

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。
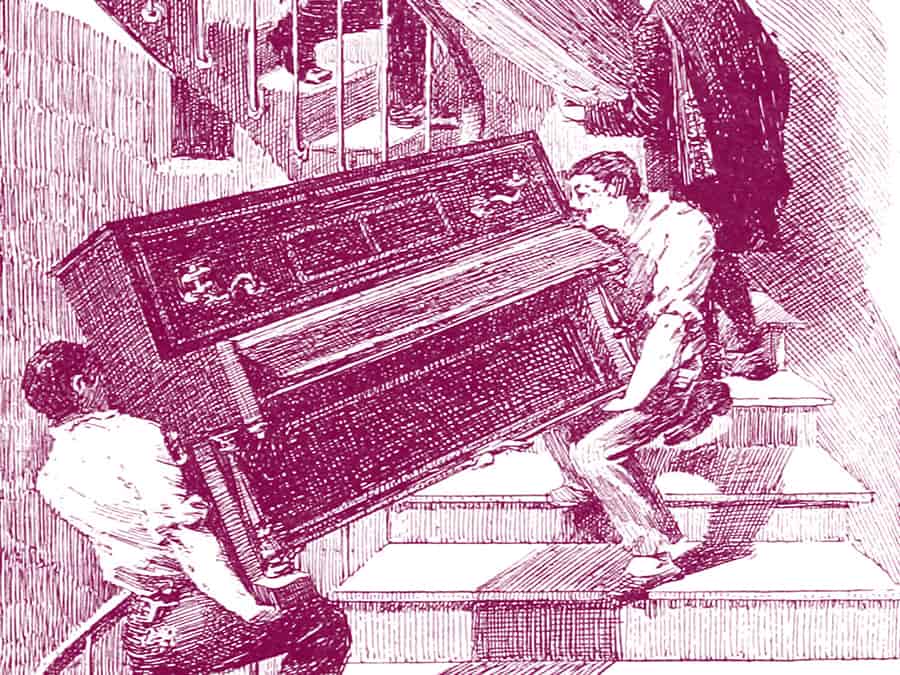
なぜ幻のピアノなのか?日本に3台しかないから?ニュースからはよくわかりません。そんなわけで、少し探っていきたいと思います。

日本の季節感と死生観を四俳人の六句を元に美しく雄大に描いた楽曲「Mado Kara Mieru」と、作曲者クリストファー・ティンについて、動画を交えながら解説。またCorner Stone Cues版と『Calling All Dawns』版の違いや、グラミー賞受賞の「Baba Yetu」についても。
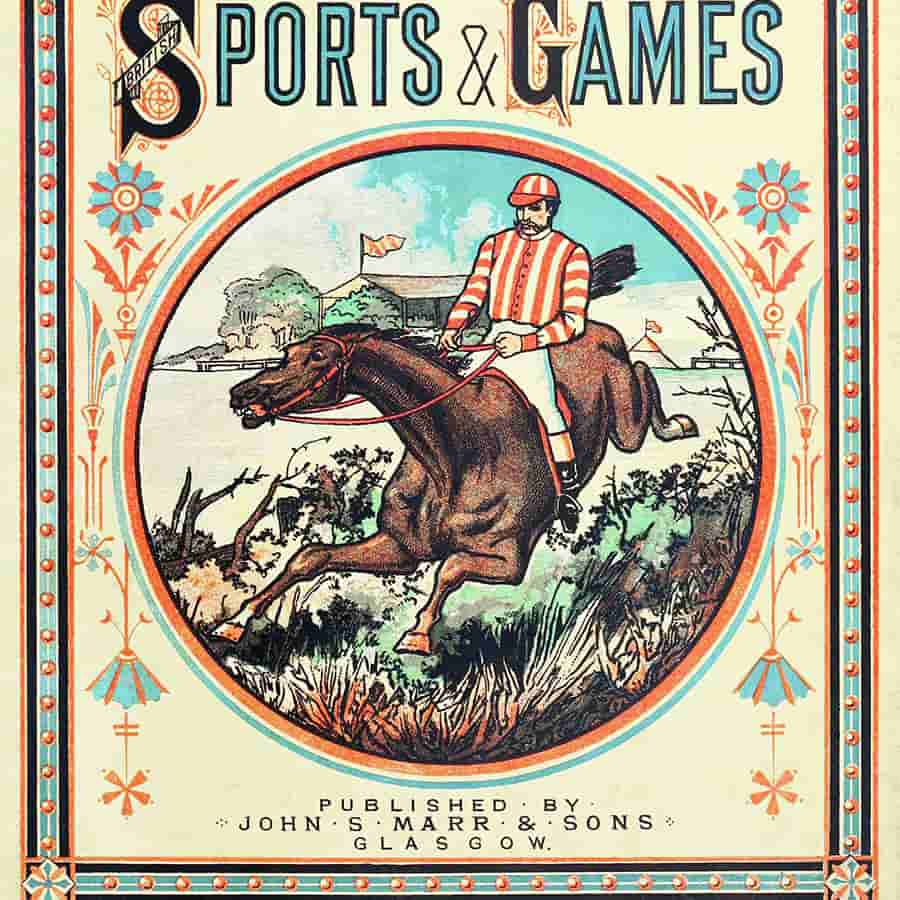
まだ感想めいたことを書いてなかったので、一応書いとこうと思います。でも、管理人はピアノの素人ですので、演奏レベルとか技術論については完全スルーしますね
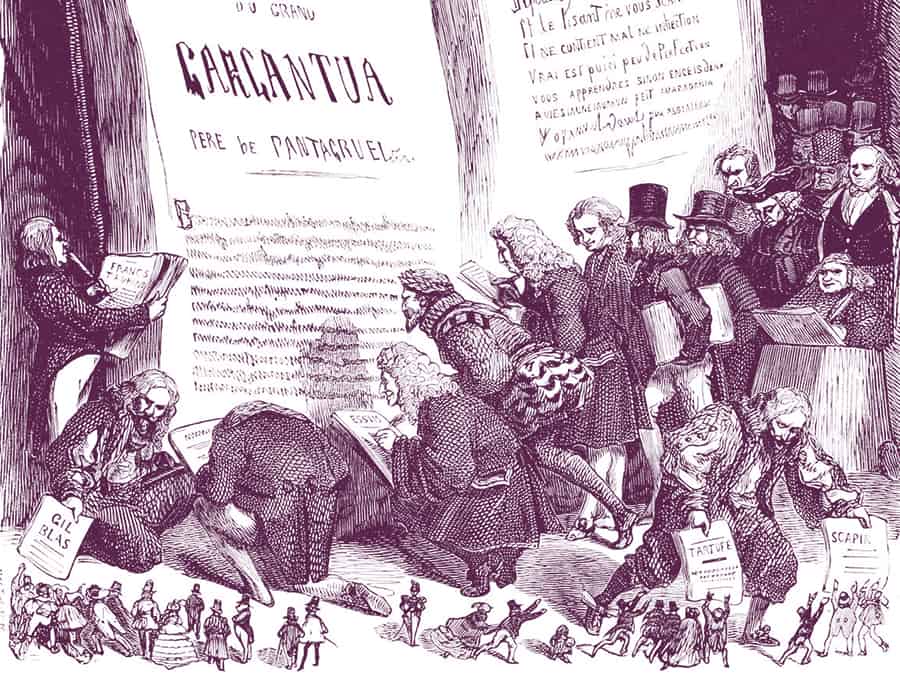
ピアノ教室管理人なんて名乗っている割に、ぜんぜん楽譜が読めないわけなんですが、「道行くあの人は楽譜が読めるのか?」というのは、割りと気になってしまうわけです。日本の識譜率、読譜率はどうなんでしょうかね?