楽器メーカーが浜松市に集中しているのはナゼ?
ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

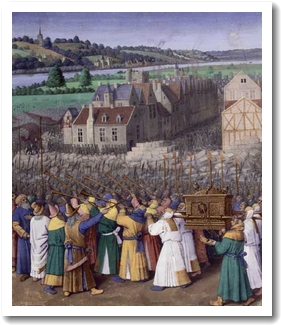 ▲旧約聖書に登場する、難攻不落のエリコの壁。(関係ないけど...)
それとは別に
ある程度、楽曲としての性格もそなえたもの、
たとえば
ツェルニーの『100番練習曲 Op.139』とかですね。
そしてもうひとつの練習曲が、
例の高難度の練習曲です。
これらは
演奏会用練習曲と呼ばれます。
本来、素晴らしい曲の条件として、
“演奏が難しい”なんてこと、必要ないんですが、
あえて、
そう、あえて難しくしている、
あるいは難しくなってしまった曲に、
言い訳のように「練習曲」ってつけちゃってるんですって。
(´゚д゚` )オイオイ
もちろん
ちゃんと練習を目的に難しくしている曲もあるんですが、
やっぱり練習というには
とっても難しそうなんですよね。
有名なところでは、
ショパンの『12の練習曲 Op.10』とか、
リストの『超絶技巧練習曲』なんかです。
『超絶技巧練習曲』って練習曲、
もう鼻血が出そうなくらい難しそうですよね〜。
ショパンの『12の練習曲 Op.10』の第3番は、
甘く切ないメロディーで人気の『別れの曲』ですが、
あれもちゃんと弾きこなそうとすると、
かなり難しいらしいですから。
りえ先生に
「なんで“演奏会用”練習曲なんていうのか、
おかしいじゃないか?」
って聞いたところ、
「これくらい弾けないようでは演奏会なんか開けないゾ、
っていう意味。」
ってテキトーにスルーされてしまいました。
(ホントかよ〜?)
というわけでまとめると、
練習曲は、
「練習曲」
・指のトレーニング系
・少し楽曲的なトレーニング系
「演奏会用練習曲」
とにかく難しいアレ。
という具合にわかれてるんですって。
(と、管理人は理解しました。)
ではお耳なおしに、
別れの曲 (ショパン) 横内愛弓
癒されるぅ〜(いろんな意味で)
(´ー`)
個人的に映画『さびしんぼう』を思い出します。
大好きです、これ。
今度のピアノ発表会でも
「練習曲」にチャレンジする生徒さんもいます。
ガンバッテくださいネ。
▲旧約聖書に登場する、難攻不落のエリコの壁。(関係ないけど...)
それとは別に
ある程度、楽曲としての性格もそなえたもの、
たとえば
ツェルニーの『100番練習曲 Op.139』とかですね。
そしてもうひとつの練習曲が、
例の高難度の練習曲です。
これらは
演奏会用練習曲と呼ばれます。
本来、素晴らしい曲の条件として、
“演奏が難しい”なんてこと、必要ないんですが、
あえて、
そう、あえて難しくしている、
あるいは難しくなってしまった曲に、
言い訳のように「練習曲」ってつけちゃってるんですって。
(´゚д゚` )オイオイ
もちろん
ちゃんと練習を目的に難しくしている曲もあるんですが、
やっぱり練習というには
とっても難しそうなんですよね。
有名なところでは、
ショパンの『12の練習曲 Op.10』とか、
リストの『超絶技巧練習曲』なんかです。
『超絶技巧練習曲』って練習曲、
もう鼻血が出そうなくらい難しそうですよね〜。
ショパンの『12の練習曲 Op.10』の第3番は、
甘く切ないメロディーで人気の『別れの曲』ですが、
あれもちゃんと弾きこなそうとすると、
かなり難しいらしいですから。
りえ先生に
「なんで“演奏会用”練習曲なんていうのか、
おかしいじゃないか?」
って聞いたところ、
「これくらい弾けないようでは演奏会なんか開けないゾ、
っていう意味。」
ってテキトーにスルーされてしまいました。
(ホントかよ〜?)
というわけでまとめると、
練習曲は、
「練習曲」
・指のトレーニング系
・少し楽曲的なトレーニング系
「演奏会用練習曲」
とにかく難しいアレ。
という具合にわかれてるんですって。
(と、管理人は理解しました。)
ではお耳なおしに、
別れの曲 (ショパン) 横内愛弓
癒されるぅ〜(いろんな意味で)
(´ー`)
個人的に映画『さびしんぼう』を思い出します。
大好きです、これ。
今度のピアノ発表会でも
「練習曲」にチャレンジする生徒さんもいます。
ガンバッテくださいネ。
この記事にはまだコメントがありません。

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。
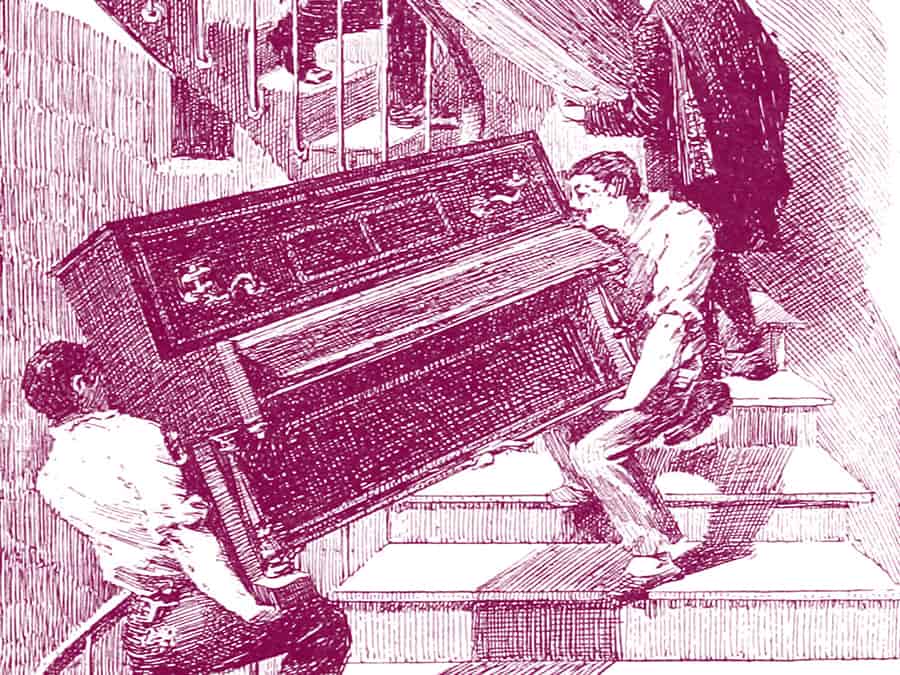
なぜ幻のピアノなのか?日本に3台しかないから?ニュースからはよくわかりません。そんなわけで、少し探っていきたいと思います。

日本の季節感と死生観を四俳人の六句を元に美しく雄大に描いた楽曲「Mado Kara Mieru」と、作曲者クリストファー・ティンについて、動画を交えながら解説。またCorner Stone Cues版と『Calling All Dawns』版の違いや、グラミー賞受賞の「Baba Yetu」についても。
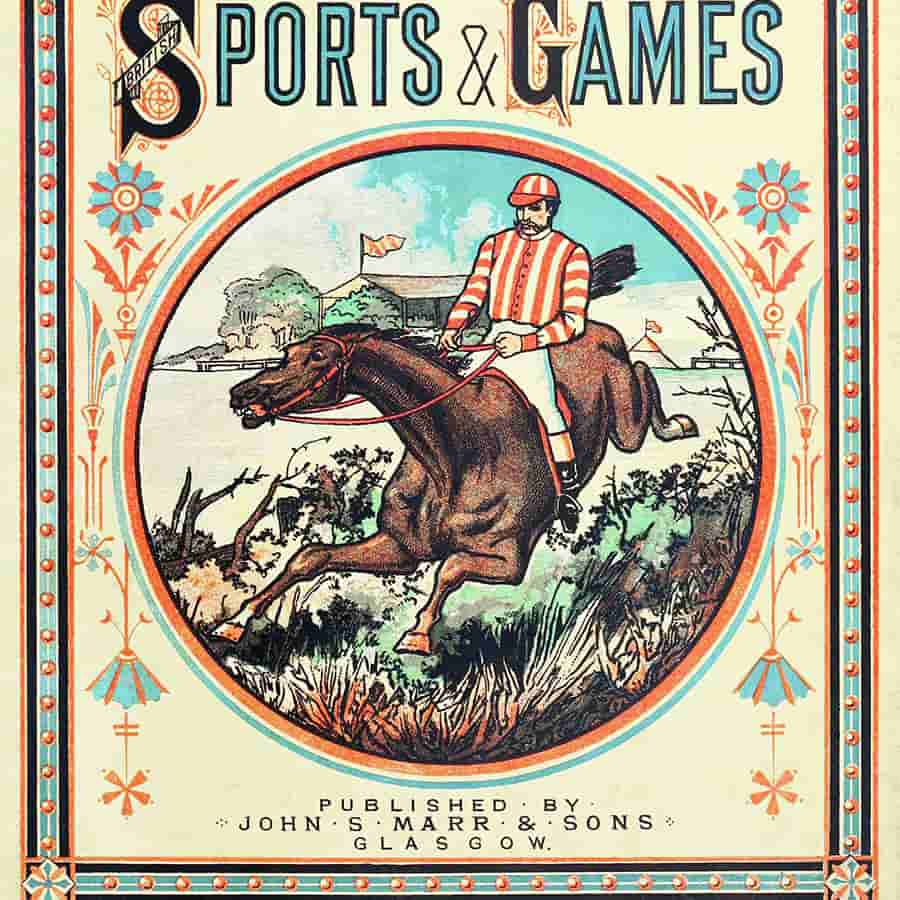
まだ感想めいたことを書いてなかったので、一応書いとこうと思います。でも、管理人はピアノの素人ですので、演奏レベルとか技術論については完全スルーしますね
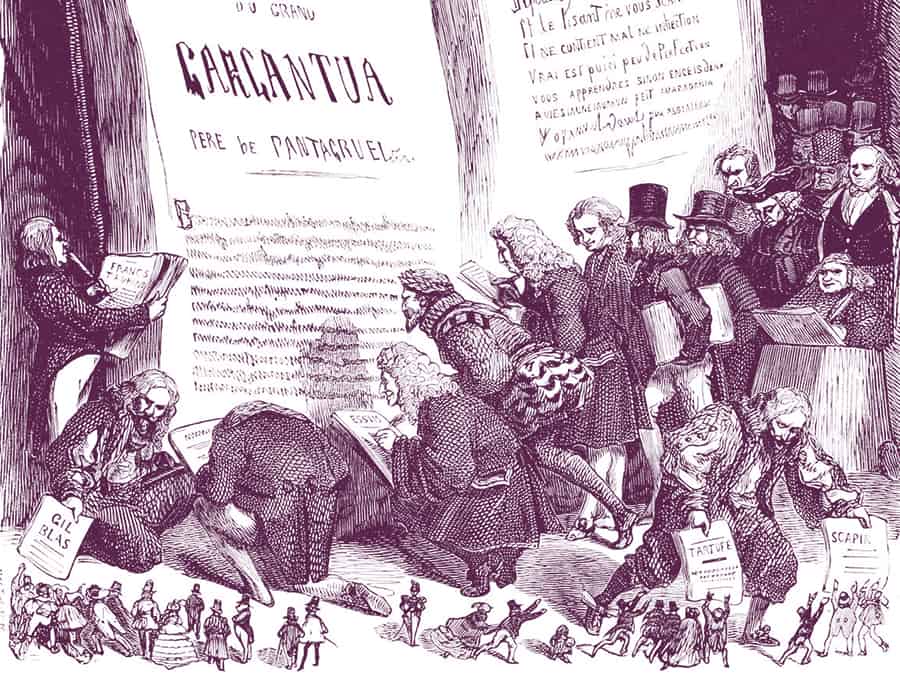
ピアノ教室管理人なんて名乗っている割に、ぜんぜん楽譜が読めないわけなんですが、「道行くあの人は楽譜が読めるのか?」というのは、割りと気になってしまうわけです。日本の識譜率、読譜率はどうなんでしょうかね?